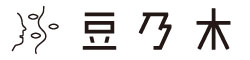こちらでは、オーガニックコーヒーを販売している方にも一読していただきたい内容です。
知っている人は知っている、のですが、知らない人は意外と知らない。
そして、「知っているつもり」になっている場合もありますので、注意深く読んでくださいね。
「オーガニックコーヒー」の謎
『フェアトレード&オーガニック生豆 豆乃木(豆乃木)』でお買い物してくださるお客様には、
「『オーガニックコーヒー』をなるべく選舞踊にしています」
という方が結構いらっしゃいます。
意外と知られていませんが、マヤビニックコーヒーの生産地メキシコは、有機コーヒー(オーガニックコーヒー)の世界トップシェアです。
マヤビニックもオーガニック栽培のコーヒーなのですが、商品名に「オーガニックコーヒー」と明記していません。
実際には、有機栽培なのに、「有機栽培」の文字も、「オーガニック」の文字も、商品名に記していません。
その理由は、有機JAS規格を満たす農産物・加工食品で無ければ「有機」等と表示した商品を”販売”することはできないからです。
つまり、このマーク!!

フェアトレードもそうですけど、認証ビジネスっていうのがあるくらいなので、必ずしも、認証がすべてではないと私は理解しています。もちろん、お金には買えない安心感があるのかもしれませんが、豆乃木では、現時点(2022年7月)では、生豆を小分けした場合、それから、焙煎したコーヒーについては、「オーガニック」と名乗ることはできないのです。
いずれ、豆乃木の商品が、ひとり歩きして行った時には、認証マークが必要になってくると思うのですが。
ということは、商品名に「オーガニック」と明記はなくても、オーガニックコーヒーであることはあります。
当店のコーヒーの9割9分がオーガニックコーヒーですが、オーがニックコーヒーと書いてないのはそのためなのです。
ちなみに、マヤビニックコーヒーのように、ちらし等の広報物の紹介の中で、「こちらのコーヒーは、メキシコのチアパス州で、マヤ先住民のひとたちによって有機栽培で育てられています」と謳うことは問題がないという認識です。*JAS法を扱う専門機関に問い合わせをしました。
「オーガニック」って本当に安全なの?
ふと、そういう疑問を持つことがあり、今回改めて、調べてみました。
日本オーガニック&ナチュラルフーズ協会さんによる回答は次の通り。
* * *
結論を先に言えば、オーガニック食品は一般の食品より安全です。
正確を期せば、「安全性が高い」あるいは「危害リスクが低い」と言うべきなのでしょうが、敢えて一般の食品と比べた場合には、安全だと言い切ってしまいます。食品の安全は、3つの危害要因(異物などの物理的危害、菌類などの生物的危害、農薬や重金属等による化学的危害)が一定以下に抑えられているときに実現します。このうち、物理的危害と生物的危害は、食品衛生法の下ですべての食品の安全性が担保されており、オーガニックが特別すぐれているわけではありません。しかし、化学的危害リスクは明確に異なります。
オーガニックは、田畑で使う資材をはじめ、加工食品の添加物についても、可能な限り化学的なものを排除していますから、化学的危害リスクは一般の食品に比べて極めて低くなっているのです。
そうは言っても、オーガニックは「化学物質不検出」を保証するものではありません。そもそも危害リスクが皆無の食品など存在しません。あくまでオーガニックと一般食品の化学的危害リスクを比較した場合に「安全」ということです。
というわけで、オーガニック=ゼロリスクは、過剰な期待といえるでしょう。
* * *
販売者にとって、食の安全を提供する上で大切なことは、認証を過信することではなく、作り手を知り、作る過程を知った上で、正しくお客様に伝えることでしかありません。
豆乃木は、これからも社会にとっても個人にとっても「健やかなよいもの」を意識して、皆さんに届けたいと思います。